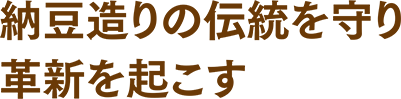株式会社 新田商店会津エリア

原材料である大豆にこだわり、昔から引き継いできた製造法を守りつつ、様々なアイデアを取り入れ新しい納豆の開発に努力する4代目 新田 俊さんにお話を伺った。


良質な大豆を安定して確保する
新田さんの納豆造りにおける一番のこだわりは、やはり大豆だという。以前は外国産の大豆を使用していたが、2011年の震災をきっかけに入手が困難となり、それ以来、国内産の大豆を探し歩き、北海道音更産の大豆“ユキシズカ”に出会った。「これが群を抜いて良質でした」と新田さんは語る。現在は栽培農家と契約を結び、良質な大豆を安定して確保できることが新田商店の強みとなっている。
『会津高田納豆』というブランド

新田商店の看板商品は『会津高田納豆』。大豆本来の味を引き出す大粒の納豆として、地元の会津地方だけでなく福島県内の大手スーパーなどでも広く販売され県民に愛されている。なかでも新田さんのおすすめは一つひとつ手作業で造る『経木納豆』だという。経木とは木を薄く削り乾燥させて造る日本伝統の包装材で、通気性と抗菌性に優れている。経木納豆はパックよりも若干柔らかく仕上がり、経木の香りがほんのり納豆につくというのが特徴だ。新田商店では赤松の経木を使っている。今では『会津高田納豆』という名の商品は、新田商店だけだという。それだけにブランド力は高い。
伝統と革新を
新田商店は経営理念として『伝統と革新』を挙げる。「既存の納豆で終わりではなく、『新しい納豆』というその先にある希望と期待を込めて納豆造りに関わる姿勢を持ち続けたいです」と力を込めて語る。乾燥納豆や納豆を粉末にしてその新しい利用法を探り、また現在も “スパイスで味わう納豆” “山塩納豆” “雪見漬(納豆の漬物)” など斬新でユニークな納豆商品をECサイト等で販売している。
「有難いことに好評をいただいています。これに留まらずこれからもいろいろな『新しい納豆』を開発していきたいです」

『会津高田納豆』を海外へ

先々代から長きにわたりお世話になっている商工会とは、新田さん自身も事業承継や法人化、設備投資に伴う補助金申請など、さまざまな場面で支援を受け、信頼関係を築いてきた。ある時、商工会からの声掛けによって福島県商工会連合会で実施している『シオクリビト事業』に参画し、そこでの専門家派遣などを通じて海外での発酵食品ブームを知った。「ぜひ海外展開へチャレンジしてみたい」と経営指導員に相談したところ、日本政策金融公庫の『トライアル輸出支援事業』の紹介を受けた。この事業を活用し、商工会・公庫と連携しながらアメリカ・ロサンゼルスでの市場調査の実施に辿り着く。その結果、納豆の味や商品パッケージに関する現地バイヤーによる生の反応を把握することができた。まだまだ海外の方々には認知度が低いという印象を受けた一方、商品に対しては好感触であり、海外市場ニーズは充分見込めるという総評を得た。
「まずは日系の方々に納豆を勧めていきたいですね。あとは体に良い発酵食品としての『会津高田納豆』の認知度をどう拡げていくかが、今後の課題だと受け止めています。」
将来的には東南アジアやヨーロッパへの展開も視野に入れ、環境志向の方に受けが良いであろう“経木納豆”や、食感を気にする方にも受け入れられやすい“乾燥納豆”など、輸出へ向けた課題克服も含め少しずつ段階的に挑戦を続けていくつもりだ。
納豆で地域おこしも
「今、『乾燥納豆』の商品化を進めています。もし間に合えば、伊佐須美神社の節分祭で初売りしたいと考えています。」この商品に、伊佐須美神社でしか購入できないという付加価値を持たせ、納豆を通じて地域観光の活性化にも貢献できないか模索している。会津美里町は、会津高田、新鶴、会津本郷の三町村が合併して誕生した。新鶴産の大豆を使用して、会津高田で乾燥納豆を製造し、本郷の流紋焼きの器に入れて伊佐須美神社で販売する計画だ。これは地域のストーリーを商品化した形となる。また、新田さん自身も鬼の格好をして節分祭に参加している。商品販売だけでなく、地域に貢献し、活性化に協力することも重要だと考えている。
『新しい納豆』に期待を込めて
最後に、新田さん自身の夢を尋ねたところ、「とりあえずは『新しい納豆』を開発したいというのが当面の夢です。何かひとつ答えを出せたらいいですね」と語り、やはり納豆造りから離れられない様子だ。まさに納豆一筋という印象を受ける回答だが、本人は納豆一途をあまり好まないようで、「何か他に趣味を見つけたいんですよ」とのこと。地域貢献の活動も含め、納豆造り以外の経験がアイデアの素になるかもしれない。新田さんの造る『新しい納豆』を食べられる日が実に楽しみである。

| 事業所名 |
|---|
| 代表者 |
| 所在地 |
| 創業 |
| 業種 |
| サポート |